木部塗装
こんにちは。
河合塗装工業営業の伴です。
今日は、豊橋市雲谷町にある現場へ行ってきました。
いよいよ作業も大詰め
外壁は完了しており、窓などの養生も外してあるため、だいぶ完成形に
近づいてきた印象です。
今日は、下屋根の上塗りをしていました。
汚れやすい下屋根は外壁を塗り終わってから仕上げ
大屋根は先に上塗りまで済ませてあるのですが、下屋根は外壁を塗るときに
塗料が飛散したり、屋根に乗って作業したりして汚れるので、
外壁が終わってから最後の上塗りをします。
通常なら、外壁の塗料が飛散しても上塗りで塗りつぶせるので
そのまま上塗りだけ行うのですが、今回は外壁に使用した塗料が
骨材(砂)入りの塗料だったため、飛散した部分にも砂が付いてしまって
ザラザラになってしまっているので、砂の付いた部分を皮スキで撤去してから塗るので
ひと手間かかります。

骨材が入っている分、いつもより遠くに飛散しやすく、養生してあった部分をだいぶ
はみ出してしまっています。

安全のためあまり広く養生できない
屋根の上に乗る作業のときに、養生のビニールがあると滑って作業にならないので、
途中の段階で飛散がだいぶつくことは折込済みだったのはありますが、
なかなか取れずケレン作業も大変そうでした。
最後に大仕事!木部塗装
一方、木部の塗装も同時進行で行います。
浴室周りにあるルーバーフェンスなのですが、この部分もなかなか
手がかかる作業です。

作業前の様子です。
すでにケレンは完了しており、これから塗装作業に入るところです。
木部には『木材保護塗料』
この部分に塗る塗料は、『ガードラックアクア』という木材保護塗料です。
木材保護塗料と一口に言っても、造膜タイプと、浸透タイプがあり、
溶剤系水性系と種類も多く、色も何色もありますが、
今回使用するのは造膜タイプの水性塗料です。
木目を活かして塗る
木材保護塗料は、もともとの木目を活かした塗り方ができる塗料で、
造膜タイプでも一般的な塗料よりも浸透させて木部を補強するようなイメージです。
浸透タイプの方がより木目が残りやすいですが、防水性は弱く、
こまめな塗替えが必要になります。
造膜タイプはその点、長持ちしやすく防水性も高くなります。

色はオークを使用します。
缶からバケツに出すと、表面に気泡がたくさん出ていました。
一旦午前の休憩に入る前に材料を用意し、しばらく置いてから塗ります。

気をつけるのは、『気泡が付かないようにすること』
塗りだすときには気泡がだいぶ収まっていました。
ルーバーフェンスは、たくさんの木の板でできているので、
重なっている部分や木部の上や横など、塗る面がたくさんあって
かなり細かい作業になります。
刷毛での地道な作業
面積も大きいので、ローラーを使用するかと思いきや、
すべて刷毛で塗るそうです。

なぜローラーを使用しないのか聞いてみたところ、
ローラーで塗ると表面に気泡が付いてしまうからなんだそうです。
気泡が付くと!?
気泡が表面についたままだと、そのまま気泡ごと固まってしまって
きれいに仕上がらないんだそう。
もっと幅の短いフェンスの場合だと、ローラーで塗ってから刷毛で気泡を潰していく
ような塗り方をする場合もあるそうですが、これだけ幅が広いと、
塗っている間に固まってきてしまってそういった方法が取れないのだそう。
刷毛なら木の模様に沿ってきれいに塗れる
木目で表面に凹凸があるので、結局刷毛で塗った方が溝にしっかり塗料が入るので、
ローラーのほうが効率的に思いましたが、結局端折らずに丁寧に塗るのが
一番だと言っていました。
塗る素材や場所によっては効率や時間短縮ばかり考えていてはきれいに仕上がらないという
ことを教えてもらいました。
なんとなくわかったような気になっていましたが、『百聞は一見にしかず』ですね。
一回塗り終わった部分です。

きれいに色と模様が出ています。
地道な作業で先は長いです。
全面、表も裏も全部刷毛で2回塗ると思うと気が遠くなるような作業ですが、
最後まで事故のないように進めてもらいたいです。
完工までもう少し、どんな仕上がりになるかが楽しみです。

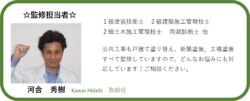
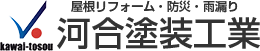

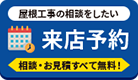
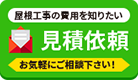
 無料診断依頼
無料診断依頼








