シーリング施工
こんにちは。
河合塗装工業営業の伴です。
今日は、豊橋市神野新田町にある現場へ行ってきました。
シーリングと外壁の張替え工事
今日は、サイディングの一部張り替えとシーリングの工事を行っていました。
家の一階部分の一部がガレージになっており、その入口部分に車をぶつけて凹んだ
痕があったため、塗装前に張り替えます。

↑施工前

↑施工後
全く同じサイディングは廃盤になっていて手に入らないため、なるべく似通った
デザインのものを使用しました。
この上からシーリングと塗装の施工をします。
施工の量が多いので2日に作業を分けて施工
シーリングの施工が多い現場なので、2日に分けて施工する予定になっており、
今日は東・北面と倉庫の施工です。
狭くて作業しづらい面も

特に、北面は倉庫との間がかなり狭く、入って行くだけでも難儀します。
幅は、ヘルメットがやっと入るくらいで、
足場が建っているためその隙間はさらに狭いです。

こんなに狭いスペースでも、職人は手慣れた様子で作業を進めていきます。
実際に隙間に入ってみるとわかるのですが、2回部分は足場が多少動くので隙間を通りやすいですが、
1階部分は足場がほぼ動かないので、隙間を通るのも一苦労です。
旧シーリング撤去後の養生作業
まずは、養生のテープを貼っていきます。

サイディングの形がボコボコしているので、テープを密着させるのもひと手間です。
テープを抑えるためのゴムローラーを使用して密着させていきます。
養生テープがしっかり密着できていないと、シーリングをきれいに打つことができません。
このゴムローラーがないと、凹凸に合わせて手で抑えないといけないので、
時短になる便利アイテムです。
金属の外壁はシリコンシーリングに注意!
倉庫は、ガルバリウム鋼板の外壁のため、目地にシーリングはありませんが、
モヤの周りやサッシの角の部分、庇の上など、細かい部分にシーリングを施工していきます。

こういった金属の外壁の場合、新築時にシリコンシーリングを使用されていることが
多いです。
シリコンシーリングは塗装と相性悪い
シリコンシーリングは、外壁塗装を行うときには不向きなシーリング材です。
塗料を弾いてしまったり、ブリードと言って、中から油が染み出る現象が起こりやすく、
塗膜の剥がれを起こしやすいからです。
ウレタンシーリングですっぽり覆う
今回は、塗装を行うため、ウレタンシーリングを使用していきますが、
シリコンシーリングはウレタンシーリングとの相性も悪く、
シリコンシーリングの上からウレタンシーリングを打ったときも同様に剥がれやすくなってしまうため、
通常の施工よりも、意識して広範囲に打つことですっぽり覆い隠して密着させるイメージです。
外壁にシリコンシーリングを使うのはなぜ?
新築時になぜ塗装と相性の悪いシリコンシーリングを打つのか聞いてみたところ、
シリコンシーリングは熱に強いからだそうです。
金属の外壁は、日光で熱くなりやすく、高温になることがあるので変成シリコンシーリングだと
傷みやすいのだそう。
ガルバリウム鋼板の場合、新築時は上から塗装を行わないため、
耐久性に優れたウレタンシーリングは使用できず、耐久性を加味してシリコンシーリングを使用するケースが
多いようです。
養生が終わったらプライマー
養生があらかた終わると、職人の一人がプライマーの塗布を始めました。
シーリング用のプライマーは臭いが強く、目に見えるところで作業していなくても、
『あっ、どこかでプライマー塗ってるな』とわかるくらいです。
プライマーは使用するシーリング材に合わせて選定するため、
窯業系サイディングでもガルバリウム鋼板でも同じ材料を使用します。
狭い箇所はプライマーを塗るのも一苦労です。
2人の職人が材料の受け渡しなどを協力しながら塗っていきます。
プライマーをしっかり塗らないと、剥がれやすくなってしまうので、やりにくい
環境でもしっかりもれなく塗って行きます。
2液タイプの材料はしっかり混ぜることが重要!

プライマー塗布まで終わったところで、シーリング材の準備をします。
シーリング材は2液タイプのものを使用するため、しっかり混ぜ合わせることが
重要です。
しっかり混ざっているか確認するために
主材と硬化剤の他に、混合確認用トナーというものが入っていました。

これは、わざと少し色のついた粉を混ぜることで、しっかり混ざっているかを
確認するためのものだそうです。
基剤と硬化剤の定義が揺らぐ


塗装に使う塗料にも2液タイプのものがありますが、
大きい缶が主材で小さい缶が硬化剤になっています。
シーリング材の場合はこれが逆で、なぜか少ない方の材料が主材です。
防水施工に使うウレタンも同様だったのですが、これがなぜかは
わからないそうです。
見た目的にも硬化剤と書いてある大きい缶が主材に見えるのですが、
これは防水の職人に聞いても知らないそうなので、答えにたどり着ける日は遠そうです。
材料の準備ができたらシーリング打ち
機械を使ってしっかり混ぜたら、シーリングガンに詰めて打っていきます。

目地の太さが途中で若干変わっている部分が多くあり、
バックアップ材がバックアップしきれていない状態です。

バックアップ材とは、断面がシルクハットのような形をした金属の板で、
サイディングの隙間に挟み込むことで目地の裏側を支え、シーリングを打つときに
材料の節約になります。
だいたい、目地の幅にピッタリ合う形で施工されているのですが、
幅が変わっている部分は隙間ができてしまっています。
サイディングに隙間ができてしまうと、水が入ってしまうので
隙間をしっかりうめていきます。
職人は動揺することもなく量を調整しながら上手に打っていました。
場数を踏んでいるだけあり、臨機応変な対応が素晴らしいです。
仕上がりを決める均し作業

シーリングを充填した部分から平らに均していきます。
ボコボコした表面ですが、手慣れたもので上手に均していきます。
剥がす時に気をつけることは『汚さないこと』
シーリングを均し終わると、養生テープを剥がしていきます。

均し終わった部分のテープは、シーリング材がべったり付着しているので、
棒を使って巻き取って手を汚さないように気を付けます。
シーリング材が手に付くとなかなか落ちないので、
壁や足場に付きやすくなってしまうので、シーリングの施工時に
養生テープを剥がす作業は意外と気を使います。
後々まで考えて作業しやすい工夫
なるべく足場の移動を少なくするため、一本の目地でも上から下まで一気に施工するのではなく、
同じ高さの足場でできる作業をまとめて行っていくイメージです。
なので作業の手順も踏まえて、養生の時点で足場の高さに合わせて養生テープを
区切ってあります。

効率よく作業を行う工夫ですね!

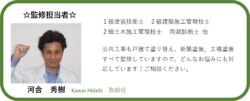
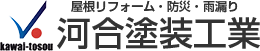

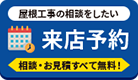
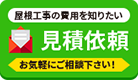
 無料診断依頼
無料診断依頼








