『紙』の養生!?
こんにちは。
河合塗装工業営業の伴です。
和風の大きなお家へ再び!
今日は、蒲郡市三谷町にある現場へ行ってきました。
和風で大きいお宅のこの現場は、前回雨戸塗装をしている様子を
見に来ました。
今日は、雨樋の塗装をしていました。
足場の動線が複雑で作業も大変!
日本瓦の屋根のこのお宅は、足場が組んであるとはいえ、現場を見るのも一苦労です。
最近多い洋風お宅は、割と総二階だったりシンプルな形状をしていることが多いので、
足場に登るときも昇降足場を
登ればぐるっと一周見れる現場が多いのですが、
屋根の形状を見てもわかるように下屋根の軒が大きくでていたり、
一周見て回るにも足場を登ったり降りたりと移動が困難です。

『塗らない部分』が多すぎて
外壁の塗装する部分も飛び飛びなので、養生も大変そうです。

塗装済みの戸箱も養生
塗装が完了している雨戸や戸箱は、他の部分を塗る際に汚れないように、
養生してありました。
塗装済みの部分の養生はくっつき注意!?
塗装が完了した部分の養生は、塗膜にビニールがくっつきやすいのが難点で、
熱などで張り付いてしまうと養生を剥がす際に塗膜が剥がれてしまうおそれが
あります。
職人によっては、養生を剥がした跡が残るのを見越して、
外壁の塗装前には付帯部の中塗りまでで止めておいて、養生を剥がしてから
上塗りを行う場合もありますが、養生を剥がしてからの上塗りは
外壁に付帯部の塗料が飛散するリスクもあります。
くっつき防止の救世主!
なので、今回は上塗りまで完了した部分の養生に、紙のマスカーを使用していました。

紙の養生は、熱によって張り付く心配もなく、これなら安心して上塗りまで
仕上げられるそうです。

『紙』なのに雨でもOK!
紙なので、雨が降っても大丈夫なのか聞いてみたところ、表面にツルツルとした
撥水の加工がしてあるため、雨が降ってもふにゃふにゃになったりすることもないそうです。
数少ない『塗る』付帯部・雨樋
雨戸や養生が終わって、今日は雨樋の塗装を行っていました。

屋根や外壁以外の部分を総称して付帯部といいますが、
このお宅は塗装する付帯部が極端に少ないです。
通常、軒天や庇、破風や鼻隠しなど付帯部と言われる部分はたくさんあり、
外壁とは色を変えて塗り分けることがほとんどです。
素材によっては塗らない方がいい場合も
しかし、下地の状態や素材によっては塗装を行わない場合もあります。
例えば、もともと無塗装の木部や、銅、アルミでできている部分は塗装は通常行いません。
塗膜が剥がれてしまうリスクがあるからです。
銅でできた部分は、青錆の色で風合いが出るので、なかなか素敵です。

鉄部は絶対塗ったほうがいい
逆に鉄でできていたりすると、サビによって腐食しやすくなってしまうので、
錆止めを使って塗装を行う必要があります。
下地を見誤ってしまうと、早期に剥がれてしまったりトラブルが起こりやすくなってしまうため、
ときには『塗らない』という選択が重要です!

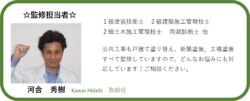
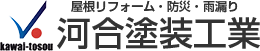

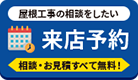
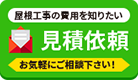
 無料診断依頼
無料診断依頼








